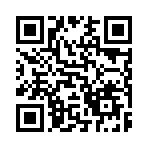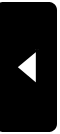秋葉神社(あきはじんじゃ)

天保2年〈1831年)、信州上諏訪の大工、立川内匠富昌らによって秋葉山の仁王門として再建された門は、明治以降 秋葉神社の随身門として伝えられてきた。鮮やかな朱 泥を塗り、屋根下に精巧な彫刻をほどこしたもので、江戸末期の秋葉山全盛期の面影を伝える唯一の建物と なっている。
秋葉神社境内には、神話の泉である機織井戸や玉垂 の滝などがあり、モリアオガエル・仏法僧・秋葉野菊 など、高山生動植物の生息地としても知られている。山項にあった上社は、第2次大戦前に焼失Lたが、 この程3年がかりで建築し、本殿が完成。61年10月に遷座祭が行なわれた。
毎年12月15日・16日に「秋葉の火まつり」が行われ、信者や見物客など多くの人でにぎわいます。
HP:秋葉山本宮秋葉神社(上社)
秋葉山本宮秋葉神社(下社)
Posted by 天竜区観光協会春野支部 at 2008年12月23日 09:42│Comments(0)
│名所・旧跡
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。